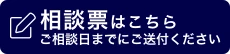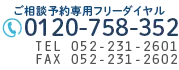顔・頭部の後遺障害認定ポイント
 交通事故によりお顔に怪我をされた場合、傷が残ってしまう外貌を損なってしまう問題は、心に与える影響が大きく、日常生活にも支障をきたします。
交通事故によりお顔に怪我をされた場合、傷が残ってしまう外貌を損なってしまう問題は、心に与える影響が大きく、日常生活にも支障をきたします。
しかし、直ちに労働能力が下がらないことも少なくないため、後遺障害等級認定がなされても、保険会社が逸失利益の支払いを拒否することがあります。そのため、相手方との交渉や裁判での主張が重要となります。
目次
頭部・顔面・頚部の後遺障害等級
| 外貌に関する障害 | |
|---|---|
| 7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
| 9級13号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
| 12級13号 | 外貌に醜状を残すもの、その他日常露出の可能性のある部分 |
頭部の損傷の裁判例
頭部外傷による高次脳機能障害について、自賠責保険での認定よりも裁判所での認定が高い等級で認定された事例についてご紹介いたします。
ケース1
自賠責保険の認定:3級→裁判所の判断:2級
自動二輪車を運転していた原告が、交差点で大型貨物自動車に衝突された事故。
この事故により、原告は右側頭部急性硬膜下血腫、脳挫傷、左側頭骨骨折等を受傷した。
頭部外傷後の後遺障害として、自賠責では後遺障害3級と認定されていたところ、裁判所において、原告の日常生活の範囲はほぼ自宅内に限定され、外出する際は看視が必要であることから後遺障害等級2級と認めるのが相当であると判断された事例。
(大阪地判平成15年1月27日)
ケース1のように、頭部損傷の影響で日常生活に支障が生じ、介護を要する程度のものであると認められた場合は、自賠責後遺障害等級は1級ないし2級となります。
もっとも、寝たきりでない場合等のように、自分で一定の行為ができる場合には「随時」介護が必要か否かの判断が難しいケースが多く、後遺障害2級と3級の境界は明確とはいえません。
そのため、早期の段階から神経学的所見の検査結果や医師の意見書、家族や職業介護人の介護記録等客観的な資料を収集することが大切といえます。
ケース2
自賠責保険の認定:非該当→裁判所の判断:7級
自動二輪車を運転していた原告が、交差点を直進していたところ、対向車線から右折してきた普通乗用自動車と衝突した事故。
事故後、病院へ搬送された際に意識があったことや頭部のCTやMRI上も脳損傷の画像所見が認められないことから、自賠責では後遺障害等級は非該当と診断されていた。
しかし、入院時から記憶障害があることや、事故後に精神症状が現れていること等から、脳損傷の程度は低いものではあるが高次脳機能障害を否定することはできないとして、後遺障害等級として7級と認めるのが相当であると判断された事例。
(名古屋地判平成24年2月24日)
ケース2では、事故直後は意識があり、脳損傷等の画像所見も認められなかったにもかかわらず、頭部に衝撃を受けていたことや、入院時に記憶障害があり、事故後に精神症状も現れていること(この事例では事故から数年後に泣きわめいたり大声を出す等の様々な精神障害が現れていると認定されています)等の事情を総合的にみて、高次脳機能障害として後遺障害等級7級相当と認めました。
脳外傷による高次脳機能障害の認定にあたっては、意識障害及び画像所見が特に重要されますが、この事例のように、事故後の病状、精神症状等について緻密に主張することによって高次脳機能障害が認定される可能性もあります。
交通事故等で頭部に衝撃を受けた場合、重症化することが多く、意識障害や感覚障害、言語障害等、損傷を受けた部分によって様々な症状が現れます。
後遺障害等級によって、加害者に対して請求できる慰謝料や逸失利益の金額は大きく異なります。
また精神障害を発症している場合には、頭部への衝撃と精神障害との因果関係を立証していく必要がありますが、精神障害については見過ごされてしまう場合もあるため、立証が難しいことが多いです。
適正な後遺障害等級を得るためにも早期の段階で専門家に相談したほうがよいでしょう。
目(眼)の後遺障害等級
目(眼)の後遺障害は、眼球の障害とまぶたの障害に分かれます。
眼球の障害には、視力障害、調整機能障害、運動障害・複視、視野障害があります。
まぶたの障害には欠損障害、運動障害があります。
それぞれの障害については、自賠責保険において後遺障害の等級認定基準が定められています。
上記の目(眼)の障害は単独で生じることはあまりなく、多くは脳損傷や頸椎捻挫等に伴って生じることから、事故後一定期間経過してから症状が判明する等して事故との因果関係が争いとなる場合があります。
眼球の障害
(1)視力障害
以下の表のとおり、視力障害としては後遺障害等級1級から13級まで認定される可能性があります。
| 視力の障害 | |
|---|---|
| 1級1号 | 両眼が失明したもの |
| 2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
| 2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
| 3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
| 4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
| 5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になたもの |
| 6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
| 7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になたもの |
| 8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
| 9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
| 9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
| 10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
| 13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
- ※ここでいう視力とは、矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズ等によって得られた視力が含まれる)をいいます。
- ※失明とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じえない者及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいいます。
視力の認定方法
視力の測定は、原則として万国式試視力表(ランドルト環による測定)を用いて検査を行います。
- 角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不等像視を生じない者については、眼鏡により矯正した視力を測定して等級認定を行います。
- 1以外の者については、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズにより矯正した視力を測定して等級認定を行います。(※なお、不等像視とは、左右両岸の屈折状態等が異なるため、左眼と右眼の網膜に映ずる像の大きさ、形が異なるものをいいます。)
- 眼鏡による完全矯正を行えば不等像視を生ずる場合であって、コンタクトレンズの装用が可能な場合には、眼鏡矯正の程度を調整して不当像視の出現を回避しうる視力により等級を認定します。
他覚的所見の資料
視力低下のみでは後遺障害認定がされませんので、他覚的所見を裏付ける検査が必要となります。
視力障害の原因としては外傷による眼球損傷や視神経の損傷などが考えられます。
眼球損傷の検査としては、細隙灯顕微鏡検査、直像鏡による検査、網膜電位図検査(ERG検査)があり、視神経の損傷としては視覚誘発電位検査(VEP検査)があります。
(2)調整機能障害
以下の表のとおり、調整機能障害による後遺障害の場合、後遺障害等級11級、12級に該当する可能性があります。
| 調節機能の障害 | |
|---|---|
| 11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害*1または運動障害を残すもの |
| 12級1号 | 1 眼の眼球に著しい調節機能障害*1または運動障害を残すもの |
- *1著しい調節機能障害
「著しい調節機能障害」とは、調整力が障害を受けなかった他眼の2分の1に減じたものをいいます。
調節力とは、明視できる遠点から近点までの距離的な範囲(調節域)をレンズに換算した値であり、単位はジオプトリ―(「D」)で表し、年齢と密接な関係があります。
- 調節力が2分の1以下に減じているか否かは、被災した眼が1眼のみであって、被災していない眼の調節力に異常がない場合は、当該他眼の調節力との比較により行います。
- 両眼が被災した場合及び被災した眼は1眼のみであるが被災していない眼の調節力に異常が認められる場合は、以下の「5歳ごと年齢の調節力」記載の年齢別の調節力との比較により行います。なお、年齢は症状固定時点の年齢で確認します。
- 被災していない眼の調節力が1.5D以下のときは、実質的な調節の機能は失われているとされることから、後遺障害の対象とはなりません。そのため、55歳以上であるときは調節力が1.5D以下であるため障害の対象となりません。
| 5歳ごと年齢の調節力 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 調整力(D) | 9.7 | 9.0 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 1.35 | 1.3 |
調節機能の検査方法
調節力の検査方法としては、アコモドポリレコーダー(遠方と近方に置かれた視標にピントが合うまでの時間の長さから調整機能障害を診断する装置)等があります。
(3)運動障害・複視
眼球の運動は、各眼3対の外眼筋の作用によって行われます。
そのため、眼筋の1個や数個が麻痺した場合には、眼球はその筋の働く反対の方向に偏位し(麻痺性斜視)麻痺した筋の働くべき方向において、眼球の運動が制限されることになります。
このような運動障害による後遺障害としては、以下の表のとおり後遺障害等級10級から13級が認定される可能性があります。
| 眼球の運動障害 | |
|---|---|
| 10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
| 11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害*2を残すもの |
| 12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害*2を残すもの |
| 13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状*3を残すもの |
- *2著しい運動機能障害
「著しい運動機能障害」とは、眼球の注視野の広さが2分の1で減じたものをいいます。また、「両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、両眼視での注視野が2分の1以下に減じたものではなく、単眼視での注視野が左右両眼とも2分の1以下に減じた場合をいいます。 - *3複視の症状
複視を生じる代表的な原因症状としては眼窩骨折(眼窩底骨折)と眼筋麻痺が考えられます。
「複視を残すもの」と認定されるためには下記の要件を満たす必要があります。
- 複視の自覚症状
- 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること(例えば滑車神経麻痺の診断がされている等)
- ヘススクリーンテストで5度以上のずれが確認できること
「正面を見た場合」に複視の症状を残す場合には10級2号、「正面以外を見た場合」に複視の症状を残す場合には13級2号に該当します。
当事務所の複視についての解決事例はこちら
もっとも、後述する目(眼)の損傷の裁判例のケース2のように、自賠責の認定基準に満たない検査結果であったにも関わらず実際上の症状等から13級2号に該当すると判断した裁判例があります。
(4)視野障害
以下の表のとおり、視野障害については後遺障害等級9級、13級に該当する可能性があります。
| 視野の障害 | |
|---|---|
| 9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
| 13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
視野とは
視野とは、眼前の1点を見つめていて、同時に見える視界の広さをいいます。日本人の視野の平均値は以下のとおりです。
| 日本人の視野の平均値(角度) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方向 | 上 | 上外 | 外 | 外下 | 下 | 下内 | 内 | 内上 |
| 調整力(D) | 60 | 75 | 95 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 |
視野障害には、1.半盲症、2.視野狭窄、3.視野変状の3つがあり、これらの障害は、8方向の視野角度の合計が、正常視野角度の合計である560度の60%以下(336度以下)になったものをいいます。
-
半盲症
半盲症とは、視神経繊維が、視神経交叉又はそれにより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半部又は左半部が欠損するものをいいます。
両眼同側の欠損するものは同側半盲、両眼の反対側の欠損するものは異名半盲といいます。 - 視野狭窄
視野狭窄とは、視野周辺の狭窄であって、これには同心性狭窄と不規則狭窄があります。 -
視野変状
後遺障害等級における視野変状は暗点と視野欠損をいいます。
暗点とは、生理的視野欠損(盲点)以外の病的欠損を生じたものをいいます。
この場合の暗点は、強い光でも全く感知できない絶対暗転をさし、ぼんやりと見える比較暗点は採用しないとされています。
視野の検査
視野の測定はゴールドマン型視野計によります。
まぶたの障害
まぶたの障害には、欠損障害と運動障害があります。
| まぶたの障害 | |
|---|---|
| 9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損*4を残すもの |
| 11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害*7を残すもの |
| 11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
| 13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損*5を残し又はまつ毛はげを残す*6もの |
| 14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛はげを残す*6もの |
- *4まぶたに著しい欠損
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆いえない程度のものをいいます。 - *5まぶたの一部に欠損
「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。 - *6まつ毛はげを残す
「まつ毛はげを残すもの」とは、まつげ縁の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。
まぶたの欠損は、外貌醜状障害としてとらえることも可能であるため、その場合には両障害のいずれか上位等級を認定することになります。
- *7まぶたに著しい運動障害
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時に瞳孔領を完全に覆うもの又は閉瞼時に角膜を完全に覆いえないものをいいます。
目(眼)の損傷の裁判例
目(眼)の障害は単独で生じることはあまりなく、多くは脳損傷や頸椎捻挫等に伴って生じることから、事故後一定期間経過してから症状が判明する等して事故との因果関係が争いとなる場合があります。
また、被害者の方の就いている職種や日常生活に与える影響等によっては、労働能力喪失率で争いになることもあります。
労働能力喪失率は、基本的には自賠責保険の労働能力喪失表を参考にすることが多いと思われます。
もっとも、日常生活や就業に与える具体的な影響如何によっては、同表以上の労働能力喪失率が認定される可能性があります。
ケース1
裁判所から視力障害の因果関係を否定された事例
原告は、事故から4か月ほど経過したころから視力障害が生じた事例。
原告について機能性弱視が疑われたものの、その症状を裏付ける器質的な異常は認められていないことや、事故から2か月程経って行われた大型免許の更新で両眼で問題なく更新できていたこと、また視力障害があるとしても過去の交通事故ですでに視力障害や視野狭窄が認定されていた等の事情から、事故との因果関係を否定しました。
(東京地判平成8年10月30日)
ケース2
自賠責保険の認定:非該当→裁判所の判断:11級
ガードレールに衝突した車両の助手席に同乗していた原告が、頭部や頸部に強い衝撃を受けて頸椎捻挫の傷害を負い、事故後1か月以上経過してから両眼に調節障害を発症した事例。
原告は事故直後、眼の異常を訴えておらず、右眼がチクチクして痛くなったために眼科を受診したのは、事故から1か月経過後でした。自賠責では原告の眼の調節障害は後遺障害に該当しないと認定しました。
しかし、裁判所は原告の症状について、光をまぶしく感じたり、ピントが合わなくなる症状がずっと続いていること、医学的に頸椎ねんざにより眼の調節障害がおこることがあるとされていること、また調節障害は事故後数週間以上経過してから発症することも多いとされていること等から、原告の両眼の著しい調節障害と本件事故との間に相当因果関係があると判断し、両眼の調節障害を後遺障害11級と認めました。
(大阪地判平成13年3月23日)
ケース3
自賠責の労働能力喪失表以上の労働能力喪失率を認定した事例
看護師であった原告が自転車で信号機のない交差点に進入し被告車両と衝突し、原告が頭部、胸部等を強打し両滑車神経麻痺、頭部外傷後遺症が残った事例。
原告には正面視の複視の後遺障害が残存しており、後遺障害認定は10級相当(労働能力喪失表上は労働能力喪失率27%)でしたが、裁判所は、「労働能力喪失率表は、労働能力の喪失を考えるに当たって合理的な基準となりうるものであるが、従事する職種等を考慮しない、一般的なものであるから、個々具体的なケースにおいては、被害者が従事していた職種等により、同表に定めた労働能力喪失率が増減する場合もありうる」等と述べた上で原告が事故後に看護師を退職せざるを得なくなったことや転職したとしても業務内容が限定される等の事情を踏まえ労働能力喪失率を40%と認定しました。
(東京地判平成18年12月25日)
ケース4
認定基準に満たない障害→裁判所の判断:13級
自転車を運転していた原告が、右方から進行してきた被告運転車両と衝突した事故。
この事故により、原告は頭部外傷や頭蓋骨骨折に加え、眼球運動障害を負いました。
自賠責の眼球運動障害(複視)の認定基準には、「ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること」が必要であるところ、原告は同目盛りで5度以上離れた位置にありませんでした。
そのため、原告の症状は上記認定基準を満たしていないことになりますが、裁判所は、原告が現に複視の症状を有していること、症状がいまだ改善していないこと、パソコンを使った仕事に支障がでていること等から、本件事故により原告に生じた眼球運動障害(複視)は後遺障害13級と認めるのが相当であると判断しました。
(さいたま地判平成24年5月11日)
耳の後遺障害
耳に関する障害は、主に(1)難聴、(2)耳鳴り、(3)耳漏に分類されます。
(1) 難聴
難聴とは、耳の伝音経路に異常が生じ、聴力に障害が出る状態をいいます。
聴力障害を生じる部位により、ア.伝音難聴、イ.感音難聴に分類されます。
ア. 伝音難聴
外耳、中耳の障害により、空気振動が十分に伝わらないため生じる難聴を伝音難聴といいます。
鼓膜の損傷、耳小骨の損傷などで生じます。
特徴として、低音や小音が聞こえにくいが、言葉の明瞭さにはあまり影響を与えません。
多くの場合、外科的手術で回復可能とされています。
イ. 感音難聴
内耳、聴神経、脳障害による難聴であり、音が聞こえにくいだけでなく、音が歪んで響いたり、言葉がはっきり聞こえない等の症状が出ます。
感音難聴は、治療による回復が困難とされています。
ウ. 混合難聴
伝音難聴と、感音難聴の両方の原因を持つ難聴を混合難聴といいます。
(2) 耳鳴り
耳鳴りとは、身体内部以外に音源がないにもかかわらず、音の感覚として認識されるものをいいます。
耳鳴りの発生には様々な原因が考えられ、内耳の炎症や損傷、腫れやリンパ液の滞留、頸椎の歪みやむち打ち、頸椎の圧力、頸部や肩の凝りなどによっても起きると言われています。
耳鳴りの原因が解明できないことも少なくなく、治療を行っても必ずしも治癒が期待できず、慢性化する場合も多いです。
(3) 耳漏 (じろう)
いわゆる、耳だれであり、外耳道から分泌されるものをいいます。
外耳、内耳の炎症、腫瘍、外傷等を原因とし、水様性、漿液性、粘性、膿性、血性など様々なものがあります。
外耳、内耳の炎症、腫瘍、外傷等を原因とし、水様性、漿液性、粘性、膿性、血性など様々なものがあります。
後遺障害の認定基準
(1) 聴力障害の基礎となる認定基準
聴力障害の認定は、①純音による聴力レベル、②語音による聴力検査結果(明瞭度)を基礎として判断されています。
(2) 難聴による障害の認定基準と等級
| 両耳の聴力障害 | |
|---|---|
| 4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
| 6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
| 6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 7級2号 | 両耳聴力が40センチメートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 9級7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声をかいすることができない程度になったもの |
| 9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
| 10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
| 11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
| 1耳の聴力障害 | |
| 9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの |
| 10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
| 11級6号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
| 耳殻の欠損 | |
| 12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
(3) 耳鳴りによる障害の認定基準と等級
耳鳴りの等級は「耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの」について12級を、「難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの」について14級を、それぞれ準用するとされています。
ここでいう「難聴」とは、平均純音聴力レベル40dB未満(聴力障害の基準を満たさないレベル)であっても、耳鳴りが存在するであろう周波数純音聴力レベルが他の周波数純音聴力レベルと比較して低下しているものをいいます。
耳鳴りの検査には、ピッチ・マッチ検査、ラウドネス・バランス検査というものがあり、これらの検査により、「耳鳴りが存在すると医学的に評価できる場合」を12級相当として取り扱います。
(4) 耳漏による障害の認定基準と等級
鼓膜の外傷性穿孔による耳漏について、手術的処置を施した場合、聴力障害が後遺障害等級に該当しない程度であっても、常時、耳漏があるものについては12級相当、その他のものについては14級相当とされています。
また外傷による高度の外耳道狭窄で、耳漏を伴わないものについては14級相当とされています。
(5) 平衡機能障害の等級
内耳の損傷による平衡機能障害については、神経系統の機能障害の一部として評価できるので、神経系統の機能の障害について定められている認定基準により等級を認定します。
(6) 耳殻(耳たぶ)の欠損(12級4号)
「耳殻の大部分を欠損」とは、耳殻軟骨部の1/2以上を欠損したものをいいますが、耳殻は左右で系列が異なるので、両耳の耳殻を欠損した場合、片耳ごとに等級を定め、これを併合します。
耳殻の欠損障害と著しい外貌醜状が競合する場合、併合とならず、上位である著しい外貌醜状の障害(7級12号)が適用されます。
耳殻軟骨部の欠損が1/2に達しない場合でも、外貌醜状の程度に達していれば、12級14号に認定することになります。
検査方法
(1) 純音聴力検査
検査音として、単一周波数からなる純音を用い、周波数、強さ、長さを変えて聞こえ方を分析的に検査します。純音気導聴力検査と、純音骨導聴力検査があり、2つの検査を組み合わせることで、障害の程度や原因となった部位などを判断します。
日を変えて3回実施され、障害等級の認定は、2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルの平均により行います。
(2) 語音聴力検査
日常使用する語音を検査音として用い、その聴こえ方を検査します。
数字を聞かせて応答させその正答率をみる語音聴取域値検査、一音節語音を使った語音聴力検査で、音圧と無関係に最高正答率(最高明瞭度)を求める語音弁別検査(言語の受聴能力を判定するもの)の2種類があります。
結果は%で表示され、検査は1回で差し支えないとされています。
(3) ピッチ・マッチ検査
耳鳴りが11周波数の純音、ハンドノイズあるいはホワイトノイズのどれに最も似ているかを調べる検査法です。
(4) ラウドネス・バランス検査
ピッチ・マッチ検査で得られた周波数音を用い、耳鳴り音の大きさと検査音の大きさとが等しくなる値を求める検査です。耳鳴り検査では、最も重要な検査といわれています。
(5) 画像検査
聴覚障害の原因が、中耳・内耳における振動伝達器官や組織の損傷による場合は、耳のレントゲン、CT、MRI撮影による検査が検討されます。
後遺障害等級認定申請上の注意点
(1) 後遺障害診断書の記載
後遺障害診断書には、聴力障害につき難聴の種類(伝音、感音、混合)、純音聴力検査結果、語音聴力検査結果の記載欄があり、医師にオージオグラム(オージオメータという検査機を用いた聴力検査の結果を表すグラフ)を添付した上で、その検査結果を記載してもらう必要があります。
また後遺障害等級認定にあたり斟酌してもらいたい症状がある場合は、別途、診断書や意見書の作成・添付を検討します。
耳鳴りに関しては、難聴ほど明確な基準が定められておらず、後遺障害診断書には「右・左」の記載欄があるのみです。しかし「労災補償障害認定必携」には検査方法が指定されているため、それに則った専門医による検査を受けた上で、検査結果や具体的な症状・程度が分かる資料を添付すべきであると思われます。
(2) 因果関係
難聴の程度が後遺障害等級認定基準を満たすものであったとしても、交通事故を原因とするものであることが立証されなければならず、因果関係が問題になり得ます。
ポイント① 事故から発症までの期間
カルテ等で、事故当初から難聴や耳鳴りを訴えていることが立証できれば、因果関係が認められる方向に働きます。
逆に、事故後、一定期間経過後に発症した場合、因果関係は否定される方向に働きます。
ポイント② 被害者側の素因
被害者に先天性聴覚障害があれば、それが主たる原因と主張される可能性があり、高齢であれば、老人性聴覚障害と主張される可能性もあります。
ほかにも、突然聴音障害を発症する「突発性難聴」という疾病があり、ストレスや疲労、ウイルス等様々な原因が提唱されていますが、判然とせず、治療法も確立されていません。
突発性難聴は増加傾向にあり、1990年代の調査でも国内で年間2万人以上が発症していると推定され、50代後半~60代前半での発症が多いです。
被害者に突発性難聴の治療歴がある場合、事故と難聴の因果関係が否定されたり、素因減額の理由とされる可能性があります。
(3) 逸失利益
耳の障害の場合は、後遺障害等級認定基準を満たしていても、等級表に記載の労働能力喪失割合どおりの認定がなされにくいと言われています。
被害者の職務遂行や、日常生活にいかに影響を及ぼしているか、実際にどの程度の収入減少を生じているか等について、具体的な主張立証を行う必要があります。
バレ・リュー症候群について
むち打ちに伴って生じる、めまいや耳鳴り等の神経症状は、「バレ・リュー症候群」と呼ばれています。 正確なメカニズムは解明されていませんが、首の損傷によって自律神経(主に交感神経)が直接的もしくは間接的に刺激を受け、発症するのではないかと推測されています。 頚部交感神経節の1つである星状神経節のブロック注射を行うことで改善される例が報告されているため、同症状に悩んでいる方は、ペインクリニックを受診し、医師に、星状神経節のブロック注射の治療を受けられないか、相談してみてはいかがでしょうか。
耳の損傷の裁判例
ケース1
被告側: 因果関係否定→裁判所の判断: 障害11級認定
原告運転のタクシーが信号待ちで停車していたところ、被告運転車両が後方から追突した事故。
この事故で、原告は頚部・腰椎捻挫の傷害を負い、耳鳴り・難聴を発症しました。
原告が耳鳴りや難聴の症状について治療を受け始めたのは、事故から1年8か月後であり、被告側は、本件事故直後から難聴が始まったのであればもっと早い時期に耳鼻咽喉科に通うはずであること、本件事故が軽微であること、他覚的聴力検査が施行されていないこと等を理由に難聴の症状と本件事故との因果関係を否定しました。
しかし、裁判所は、本件事故の態様、原告の負傷部位や負傷の程度、難聴を訴えた時期や難聴に対する治療を受けるに至った経過、本件事故前の状態、既往歴等を検討した結果、原告は本件事故により、頚部・腰椎捻挫の傷害を負い、それにともない耳鳴り・難聴の症状が発現したと認め、後遺障害11級に該当すると認めるのが相当であると判断しました。
(大津地判平成9年1月31日)
ケース2
自賠責保険の認定: 14級→裁判所の判断: 11級
自転車を運転していた原告が、右方から進行してきた被告運転車両と衝突した事故。
高速道路において、被告運転車両が原告運転車両を追い越した直後にスリップして、非常帯の壁に激突し、その反動で原告車両に衝突した事故。
この事故で、原告は右難聴、右耳鳴りの症状が残存し、自賠責にて後遺障害等級14級と認定されました。
裁判所は、後遺障害等級の認定基準について、14級は「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」、11級は「1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」と定められているところ、原告の純音聴力検査の結果は、ステロイド剤の投与のころに一時期比較的良好な時期があったものの、それ以外は、一貫して80デシベル以上であることからすれば、物損請求事件や本件訴訟における尋問状況を考慮しても、少なくとも後遺障害等級11級に該当するものと認めるのが相当であると判断しました。
(岡山地判平成21年5月28日)
ケース3
他覚所見がない難聴、耳鳴りにつき、自賠責非該当→裁判所の判断: 14級相当以上の後遺障害を認めたケース
事故により頭部を強打したタクシー運転手がむち打ち症、両耳鳴り、両感音性難聴で治療を受け、自賠責では非該当とされましたが、異議申立後に耳鳴り、難聴で14級相当と認定されました。
事故後の症状で通常勤務に戻れず退社し、他社のアルバイト運転手として稼働していることや、後遺障害の内容、程度、年齢、職種、転職状況が考慮されました。
裁判所は8年間14%の逸失利益をみとめ、後遺障害慰謝料190万円を認定しました。
通常、後遺障害14級の場合、労働能力喪失率は5%程度と言われているため、通常の14級相当以上の後遺障害が認められたことになります。
(岡山地判平成5年4月23日)
ケース4
自賠責: 14級相当の難聴→裁判所の判断: 自賠責の判断を認め、耳鳴りを否定したケース
事故により頸椎捻挫等の傷害を負った原告が、半年の通院加療後、左耳鳴り、左感音性難聴、左耳管狭窄症を主張しましたが、自賠責が左耳難聴について14級3号、耳鳴りは他覚的に証明し得ないと判断されました。
裁判所は、自賠責の判断を前提に、19年間5%の逸失利益、慰謝料100万円を認定しました。
(横浜地判H8.4.25)
ケース5
原告側: 難聴は事故に起因する後遺障害と主張→裁判所: 高度の難聴が突発性難聴の可能性があるとし、因果関係を否定したケース
本件事故で原告が頭部外傷を負っており、脳震盪による難聴の可能性があり得ることを認めつつも、原告が明確に難聴を訴えたのが事故後約7か月後であること、突発性難聴の可能性が否定できないことを考慮し、本件事故による難聴との蓋然性の立証がないとして、裁判所は難聴での後遺障害を否定しました。
(大阪地判H8.1.29)
ケース6
自賠責: 非該当→裁判所: 耳鳴り、パニック障害と事故との因果関係を認めたが、突発性難聴の治療歴や心因的影響を考慮し、4割の素因減額をしたケース
原付で転倒した原告が、頸椎捻挫、左耳鳴り等で14級相当の障害を主張しましたが、自賠責は非該当となりました。もともと原告は、パニック障害、高血圧症、耳鳴り等の受診歴ありました。
裁判所は、本件事故の態様はパニック障害を有する原告にとって大きな精神的動揺を与え、耳鳴りを悪化させたとし、逸失利益48万、後遺障害慰謝料110万を認定しました。
ただし耳鳴りは少なくとも6年前から症状があり、突発性難聴の治療歴もあり、そもそも耳鳴りの原因は心因的な要因が大きいとして、4割の素因減額となりました。
鼻の後遺障害
| 9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
|---|
口の後遺障害
はじめに
口の後遺障害には、咀嚼機能障害、言語機能障害、歯牙障害があります。
また、等級に直接該当はしませんが、開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要する場合、嚥下障害、味覚障害に関しても、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とすることになっています(自動車損害賠償保障法施行令別表第2備考6)ので、これらの後遺障害についても説明します。
咀嚼及び言語機能障害等
区分等級
以下の表の通り、6段階に分かれています。
| 咀嚼・言語の機能障害 | |
|---|---|
| 1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
| 3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
| 4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
| 6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
| 9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
| 10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
認定基準
咀嚼機能障害は、上下咬合、配列状態及び下顎の開閉運動等によって総合的に判断されます。
-
咀嚼機能を廃したもの
流動食以外は摂取できないものをいいます。 -
咀嚼機能に著しい障害を残すもの
粥食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。 -
咀嚼機能に障害を残すもの
固形食物の中に咀嚼できないものがあること、または、咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。
検査方法
咀嚼機能検査は存在していますが、現時点では、後遺障害等級認定では要求されていません。後遺障害診断書の記載、咀嚼状況報告書並びに頭部及び口腔の画像を提出します。
開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要する場合
認定基準
開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要する場合は、12級相当になります(自動車損害賠償保障法施行令別表第2備考6)。
「開口障害等を原因として」とは、開口障害、不正咬合、咀嚼関与筋群の脆弱化等を原因として、咀嚼に相当時間を要することが、医学的に確認できる場合のことをいいます。
検査方法
咀嚼機能障害に準じます。
嚥下障害(嚥下とは、食物を認識してから口に運び、取り込んで咀嚼して飲み込むまでのことをいいます。)
認定基準
舌の異常、咽頭支配神経の麻痺等による嚥下障害は、その障害の程度に応じて、咀嚼機能障害にかかる等級に準じて相当等級を認定することになっています。
嚥下機能を廃したものは3級相当、嚥下機能に著しい障害を残すものは6級相当、嚥下機能障害を残すものは10級相当になります(自動車損害賠償保障法施行令別表第2備考6)。
検査方法
咽頭刺激、水飲みテスト、反復唾液嚥下テスト(RSST)を行い、異常が認められる場合には、さらに、ビデオ嚥下造影検査(VF)、または、嚥下内視鏡検査(VE)をします。
味覚障害
認定基準
味覚脱失は12級相当、味覚減退は14級相当になります(自動車損害賠償保障法施行令別表第2備考6)。
-
味覚脱失
ディスク法による最高濃度液での検査により、基本4味質(甘味、酸味、塩味、苦み)が、すべて認知できないものをいいます。
味覚減退とは、濾紙ディスク法による最高濃度液での検査により、基本4味質(甘味、酸味、塩味、苦み)のうち、いずれか1味質以上を認知できないものをいいます。 -
味覚減退
日時の経過により、ある程度回復することが多いため、原則として、症状固定とされてから、6カ月を経過してから、等級の認定を行うことになっています。
検査方法
甘味、酸味、塩味、苦みの4種類の味質について5段階の濃度液を用意し、これを浸した濾紙を検査部位(舌)に置き、どの味質を回答してもらうという濾紙ディスク法によります
なお、現在は、うま味を加えた5つが基本味質とされていますが、うま味は、後遺障害等級の認定の対象にはなっていません。
言語機能障害
認定基準
-
言語の機能を廃したもの
4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音)のうち、3種以上の発音不能のものをいいます。 -
言語の機能に著しい障害を残すもの
4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は(語音が一定の順序に連結され、それに特殊の意味がつけられて言語ができあがること)機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。 -
言語の機能に障害を残すもの
4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいいます。
語音の説明
語音は、口腔等附属管の形の変化によって形成されますが、この語音を形成するために、口腔内附属管の形を変えることを構音といいます。子音を構音部位に分類すると、次の4種類になります。
- 口唇音…(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
- 歯舌音…(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
- 口蓋音…(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
- 咽頭音…(は行音)
検査方法
標準失語症検査(SLTA)等があります。
声帯麻痺等による著しいかすれ声
認定基準
声帯麻痺等による著しいかすれ声は、第12級相当となります(自動車損害賠償保障法施行令別表第2備考6)。
検査方法
咽頭ファイバースコープ検査等があります。
歯牙障害
区分等級
以下の表の通り、5段階に分かれています。
| 歯牙の障害 | |
|---|---|
| 10級4号 | 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 11級4号 | 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 12級3号 | 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 13級5号 | 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 14級2号 | 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
認定基準
歯科補綴(ほてつ)を加えたものとは、現実に喪失(抜歯を含む)又は著しく欠損(歯冠部の体積4分の3以上を欠損)した歯牙に対する補綴、及び、歯科技工上、残存歯冠部の一部を切除したために歯冠部の大部分を欠損したものと同等な状態になったものに対して補綴したものをいいます。
補綴とは、喪失または欠損した部分について、人工物により補うことをいいます。
交通事故以前に、既に歯科補綴を加えた歯が存在していた場合には、既存障害として扱い、交通事故により生じた障害歯の本数に既存障害歯の本数を加えた結果、上位等級に該当することになった時には、後遺障害等級においては、加重障害として扱われます。
重い虫歯(C4レベル)は、著しく欠損した歯牙として、既存障害歯と認定されます。
例えば、既存障害歯が4本あり、交通事故により障害歯が3本生じて補綴した場合には、7本を歯科補綴したとして、12級となりますが、既存障害として、14級を控除します。
通常の後遺障害診断書の書式とは異なり、歯科用の後遺障害診断書の書式が用意されているので、注意が必要です。
歯科医が後遺障害診断書を書く機会は少なく、既存障害歯の記載が抜けていることもありますので、虫歯等による既存障害歯がないかを事前に確認しておく必要があります。
検査方法
通常、補綴後のパノラマX線写真を歯科医院で撮影して、提出します。
裁判例
逸失利益について
口の障害は、直接的に労働能力に影響を及ぼすことは少なく、他の障害と比較して少ないと考えられているため、逸失利益は否定されることが多いです。
もっとも、被害者が現在従事している職業や将来の職業選択の可能性、その他日常家事に与える影響等を考慮し、逸失利益を認めている例もあります(ただし、労働能力喪失率や労働能力喪失期間が制限される場合が多い)ので、以下では、逸失利益を認めた裁判例を紹介します。
ケース1
原告: 咀嚼障害、歯牙障害による労働能力喪失を主張→裁判所: 歯牙障害に関して労働能力喪失を否定
大阪地判平成27年10月1日(自保1964号51頁)
本件では、飲食業に従事する男性について、以下の通り、咀嚼障害に関しては労働能力喪失を認めましたが、歯牙障害に関しては否定しました。
「後遺障害等級表併合9級の認定を受けた原告の後遺障害は、前記のとおり、③同表14級2号に該当する歯牙欠損及び骨植不良、①同表10級3号に該当するそしゃく障害及び開口障害、②同表12級13号に該当する左口角、左鼻翼から頚部までの感覚消失、アロデニアの3つである。このうち、まず、①そしゃく障害は、飲食業に従事する原告にとって、食材や酒類の調達で重い物を持ち上げる際に、噛み合わせが悪いことによって支障が生じると考えられる上、調理にも支障を及ぼしうるものといえる。原告が、将来的にも飲食業への従事を続ける意向を示していることからすると、生活の適応により労働能力喪失率の逓減があると思われるとはいえ、労働能力への影響は小さいとはいえない。他方、③歯牙欠損は、一般的には労働能力に与える影響は少ないと考えられる上、原告が矯正と補綴の治療を受けていることなども考慮すると、労働能力に直接大きい影響を及ぼすものとまでは認め難い。
以上に加えて、飲食店で接客を行う原告にとっては、②顔面等の感覚消失や流涎も些細な障害とは言い難いことなども踏まえると、原告の労働能力喪失率は、当初の5年間は35パーセント、それ以降67歳までの27年間は20パーセントと認めるのが相当である。」
ケース2
裁判所: 歯牙障害で後遺障害逸失利益7%を認めたケース
名古屋地判平成25年4月19日(平成24年(ワ)1339号)
本件では、パンの製造に使用する風味改良剤等の営業販売をしている被害者について、以下の通り、歯牙障害について、労働能力喪失を認めました。
「原告は、パンの製造に使用する風味改良剤等の営業販売に従事しており、風味、食感、口溶け、味等を確認するために、最低でも10回、多いものでは50回以上パンを咀嚼して試食する必要がある。
そうしたところ,原告には,下顎骨骨折に伴う咀嚼障害,開口障害により咀嚼に相当時間を要し(12級)、歯牙欠損等により3歯以上に歯科補綴を加えた(14級)後遺障害が残存している(併合12級)。
原告の職務内容に照らせば、咀嚼に相当時間を要することや3歯以上に歯科補綴を加えたことが何ら労働能力に影響を及ぼさないとは考え難く、原告に現実の減収は生じていないものの、原告の特段の努力によるものとして後遺障害逸失利益の発生を認めるのが相当である。
原告の平成21年における実収入298万5574円を基礎収入とし、労働能力喪失率については、後遺障害の内容や程度、職務内容等を総合するに7%とし、就労可能年数27年の後遺障害逸失利益306万0243円(298万5574円×7%×14.6430)を認めるのが相当である。」
後遺障害慰謝料について
逸失利益が否定された場合でも、後遺障害慰謝料の算定の際に、考慮する場合もありますので、以下では、後遺障害慰謝料で考慮した裁判例を紹介します。
ケース3
原告側: 労働能力喪失を主張→裁判所: 労働能力喪失は否定、後遺障害慰謝料を増額
東京地判平成14年1月15日(交民35巻1号1頁)
本件では、交通事故により受傷し歯牙障害(12級)及び外貌醜状(12級)の後遺障害(併合11級)を残した被害者について、労働能力喪失は認められませんでしたが、以下の通り、後遺障害慰謝料を増額しました。
「原告の一二級三号に該当する歯牙障害については、前記のとおり、これによる労働能力の喪失は認められないが、原告は、本件事故により九歯を失ったのに加えて、ブリッジ治療の必要上、さらに四歯に補綴を加え、結局、本件事故のため、合計一三歯もの健康な歯に補綴を加えなければならない結果となったものである(ちなみに、自賠法施行令二条別表は、一〇歯以上に対し歯科補綴を加えた場合を一一級四号に、一四歯以上に対し歯科補綴を加えた場合を一〇級三号に該当するものとしている。)。そして、いまだ独身の身である原告にとって、上の前歯五歯についての取り外し式の局部床義歯は、生活上の不便をもたらすことに加えて、精神的にも相当な苦痛を与えるものと推察される。したがって、これらの点は後遺障害慰謝料の増額事由として考慮すべきである。
さらに、一二級一三号に該当する外貌醜状については、前記のとおり、これによる直接的な労働能力への影響は認められないものの、原告が、瘢痕の存在を気にして、対人関係や対外的な活動に消極的になることはあり得ないではなく、これが間接的に労働の能率や意欲に影響を及ぼすことは考えられるから、この点も後遺障害慰謝料の増額事由として考慮すべきである。
以上のとおり、歯牙障害と外貌醜状のいずれについても後遺障害慰謝料の増額事由が認められることにかんがみると、原告に対する後遺障害慰謝料の額は、通常の併合一一級の後遺障害に対する慰謝料額(裁判実務上は、三九〇万円とされるのが普通である。)にその三分の二を加算した六五〇万円とするのが相当である。」
結語
後遺障害の種類によって、必要な検査や書類が異なりますので、後遺障害の認定に関しては、弁護士に相談していただくことをおすすめします。