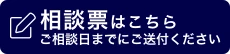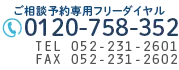賠償請求できる損害
保険会社が提示する賠償額は低い場合が多い
賠償請求できる損害の内容についてご説明する前に、前提として、賠償額算定には3つの異なる基準があります。

①自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の基準
自賠責保険とは、自動車、バイク(二輪自動車、原動機付自動車)を使用する場合に、自動車損害賠償保障法により、全ての運転者が加入を義務付けられている損害保険で(強制保険)、人的損害にのみ適用されます。
最低限の損害賠償金を被害者が受け取れるようにすることを目的とする保険なので、この自賠責保険の基準に従って損害額を算定すると、低額になります。
②任意保険の基準
交通事故の被害者に生じる損害額は、自賠責保険から出される保険金を上回ることがほとんどです。
自動車運転者は、自賠責保険のみだと、自賠責保険の保険金を超える部分の損害額を自身で負担しなくてはならなくなります。
そこで、自動車運転者の多くは、自賠責保険の保険金を超える部分の損害に対する保険金を出してくれる任意保険にも加入しています。
したがって、交通事故の被害者は、加害者が任意保険に加入している場合は、自賠責保険基準よりも多額の賠償額を受け取れることが多いです。
しかし、任意保険を提供しているのは、民間の損害保険会社であり、利潤追求のために、交通事故の被害者に対して払わなくてはならない保険金の額をなるべく低くしようとしてきます。
任意保険の基準は、各保険会社によって多少違いますが、裁判の基準と比べると低額なことが多いです。
③ 裁判の基準
交通事故の被害者の損害額について裁判所と弁護士会が協議して作成した基準が存在し、裁判ではこの基準で損害額が認定されることが多いです。
そして、この裁判の基準は、自賠責保険や任意保険の基準よりも高額なのが通常です。
保険会社は、任意保険の基準や、時には、自賠責保険の基準に従い、保険金額を提示しますが、被害者としては、裁判の基準を持ち出して、裁判も辞さないとの態度で保険会社と交渉すると、受け取れる保険金額が増加する可能性があります。
しかし、裁判の基準や裁判手続きは、高度に専門的で、被害者の方のみでは対処が困難なのが現実です。
そこで、裁判の基準や裁判手続きの専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
事故による受傷から死亡するまでの損害
事故により即死した場合を除き、受傷してから死亡するまでにも治療費等の損害が発生し、被害者の相続人は、これらの損害を賠償請求することができます。
① 治療費
被害者の受傷時から死亡時までに要した治療費は、被害者の損害と認められ、被害者の相続人は、賠償請求することができます。
もっとも、治療にかかった全額を請求できるのではなく、必要かつ相当な治療行為の費用のみを請求できます。
治療行為として必要性、相当性が否定される場合は、その費用を請求することができないので、注意が必要です。
たとえば、通常必要とされる診療行為を超えて行われるような、医学的必要性や合理性が否定される診療行為(=これを過剰診療と言います。)や、報酬額が特段の事由がないにもかかわらず社会一般の診療費水準に比して著しく高額な診療行為(=これを高額診療と言います。)に要した費用については賠償請求できない可能性があります。
保険会社の示談案では、必要かつ相当な治療行為とされていなくても、裁判では必要かつ相当な治療行為と認められることもあるので、保険会社の示談案に納得がいかない場合は、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
② 入院雑費
死亡事故以外の被害者は、入院中、日用品雑貨費(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費など)、栄養補給費(牛乳、バター等購入費)、文化費(新聞雑誌代、テレビ賃借料など)などの治療費以外の支出を余儀なくされますが、これらの諸雑費の支出について個別的に立証し、損害としての相当性を判断するのは著しく煩瑣なので、損害額は、1日当たりの定額で計算されます。
自賠責保険の基準では1日につき1100円とされ、任意保険の基準でも1日につき1100円前後とされることが多いです。裁判の基準では1日につき1500円とされます。
死亡事故の被害者の場合、症状が重篤で、上記のような日用品雑貨費等を支出することはあまりないですが、入院に際してはほかにも様々な費用が掛かりますので、上記金額が被害者の損害として認められ、被害者の相続人は、賠償請求することができます。
③ 通院交通費
交通事故で受けた傷害の治療のために通院をする際にかかった交通費は損害として認められ、被害者の相続人は、賠償請求することができます。
公共交通機関を利用した場合の往復の交通費は、全額認められます。
自家用車等を利用した場合には、その必要性、相当性があることが前提ですが、往復のガソリン代、高速道路料金及び病院等の駐車場料金等が損害として認められます。
タクシー代は、タクシー利用の必要性、相当性が認められる必要があります。必要性、相当性は、傷害の部位・程度、被害者の年齢、駅や病院までの距離、代替交通機関の存否・内容等の事情を総合考慮して判断されます。たとえば、軽い打撲傷による通院の際にタクシーを利用した場合は、タクシー利用の必要性、相当性が否定され、タクシー代の請求が否定される可能性があるでしょう。
もっとも、タクシー代の請求が否定された場合でも、公共交通機関の運賃・利用料の範囲内で交通費が認められます。
④ 付添看護費
④-1 入院付添費
付添看護が必要との医師の指示がある場合はもちろん、医師の指示がなくとも、受傷の程度、被害者の年齢等により、客観的に付添看護の必要性が認められる場合、付添人に対してかかる費用が損害として認められます。
なお、付添人の交通費や宿泊費も別途、損害として認められます。
付添人が職業付添人の場合は、実費が損害として認められます。
付添人が近親者の場合は、損害額は1日あたりの定額で計算されており、自賠責保険の基準では1日につき4200円とされ、任意保険の基準でも1日につき4200円とされることが多いです。裁判の基準では1日につき6500円とされています。
保険会社からの示談案の中には、入院付添費が入っていないこともあるので、注意が必要です。
④-2 通院付添費
死亡事故の被害者は症状が重篤で、通院のためには、通常、付添人が必要になります。
この付添人に対してかかる費用が損害として認められます。なお、付添人の交通費も別途、損害として認められます。
付添人が職業付添人の場合は、実費が損害として認められます。
付添人が近親者の場合は、損害は1日あたりの定額で計算されており、自賠責保険の基準では1日につき2050円とされ、任意保険の基準でも1日につき2050円とされることが多いです。裁判の基準では1日につき3300円とされています。
保険会社からの示談案の中には、通院付添費が入っていないこともあるので、注意が必要です。
④-3 自宅付添費
死亡事故の被害者が、自宅療養した場合、自宅付添費が損害として認められる可能性があります。
付添人が職業付添人の場合は、実費が損害として認められます。
付添人が近親者の場合は、損害は1日あたりの定額で計算されており、自賠責保険の基準では1日につき2050円とされ、任意保険の基準でも1日につき2050円とされることが多いです。
裁判の基準では、明確な基準はありませんが、必要かつ相当な金額とされます。ただし、入院付添費よりは低額となることが多いです。
保険会社からの示談案の中には、自宅付添費が入っていないこともあるので、注意が必要です。
⑤ 休業損害
被害者は、受傷時から死亡時までの期間に、休業をしなければ得られたはずの収入が休業損害として認められ、被害者の相続人は、賠償請求することができます。
ア 給与所得者の場合
・自賠責保険の基準
休業1日あたりの損害が5700円とされるのが原則ですが、交通事故前の1日あたりの収入が5700円を超えることが明らかな場合には、19000円を限度として、その実額が1日あたりの損害とされます。
計算式:(5700円~19000円)×休業日数
・任意保険の基準
裁判の基準と近い額で支払いがなされることが多いです。
・裁判の基準
交通事故前3か月の給与額の合計を90で割って、1日あたりの基礎賃金を算出し、それに休業日数をかけた額を損害として認定するのが通常です。
計算式:交通事故前3か月分の給与額の合計÷90×休業日数
イ 事業所得者の場合
・自賠責保険の基準
1日あたりの損害は原則として5700円とされ、それに休業日数をかけた額が休業損とされます。
計算式:5700円×休業日数
・任意保険の基準
裁判の基準と近い額で支払いがなされることが多いです。
・裁判の基準
事故前年の確定申告所得額を基礎に、1日あたりの所得額を算出し、それに休業日数をかけた額を損害として認定するのが通常です。
計算式(事業期間が1年であった場合):事故前年の確定申告所得額÷365×休業日数
しかし、年度により所得額に相当の変動がある場合その他前年度の所得額を基礎に算定するのが不適当と考えられる場合は、事故前数年分の所得の平均額をもとに1日あたりの所得額を算出します。
さらに、事業を継続するうえで、休業中も支出を余儀なくされる家賃・従業員給料などの固定経費も相当性が認められる限り、休業損害に加えることができます。
事業所得は何を経費として差し引くのかなど、額を判断するのが難しいので、保険会社の提示額と被害者の主張する額が異なり、もめるケースが散見されます。そのように場合は、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
ウ 会社役員の場合
・自賠責保険の基準
1日あたりの損害は原則として5700円とされ、それに休業日数をかけた額が休業損害とされます。
・任意保険の基準
裁判の基準と近い額で支払いがなされることが多いです。
・裁判の基準
役員報酬は、労務提供の対価の部分と、利益分配の部分があります。そのうち、前者の労務提供の対価の部分は、給与所得者の給与と性質が同じなので、1日あたりの労務提供の対価に休業日数をかけた額が損害として認定されます。
一方、後者の利益分配の部分は、休業していても受け取れる性質のものなので、休業損害とは認められません。
役員報酬のうち、労務提供の対価として認められる額がいくらかで保険会社の主張と被害者の主張が対立することがあるので、ここでもやはり弁護士等の専門家に相談するのをお勧めします。
エ 学生の場合
・自賠責保険の基準
学生の休業損害について言及されていません。
・任意保険の基準
休業損害は認められません。
・裁判の基準
原則として休業損害は認められません。
もっとも、アルバイト収入があれば、それを基礎に休業損害が認められる場合があります。
交通事故で受けた傷害の治療のため、学校の卒業、就職の時期が遅延した場合は、予定通り就職していたのであれば得られたはずの給与額が損害として認められます。
オ 家事従事者の場合
・自賠責保険の基準
1日あたりの損害は原則として5700円とされ、それに休業日数をかけた額が休業損害とされます。
・任意保険の基準
自賠責保険の基準と同様、1日あたりの損害は5700円とされます。
・裁判の基準
女性労働者の全年齢平均賃金額(全女性労働者の平均賃金)を基礎として、1日あたりの賃金額を算出し、それに休業日数をかけた額が、休業損害とされます。
高齢者の場合、全年齢の女性労働者ではなく、その年齢の女性の平均賃金額を基礎にして、休業損害額が算出されるため、低い額になります。それでも任意保険の基準よりは高い額となるのが通常です。
弁護士が代理していない場合、保険会社からの損害額の提案の中に、家事分の休業損害
がほとんど入っていないことがあります。また、実際に通院した日のみ家事分の休業損害を認めている場合もあります。そのような場合には、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
カ 無職者の場合
・自賠責保険の基準
無職者の休業損害について言及されていません。
・任意保険の基準
休業損害は認められません。
・裁判の基準
失業状態が継続するであろう場合は、休業損害は認められません。
現在無職でも、就職が内定している等就労の予定が具体化している場合は、就労予定日から症状固定時までの休業損害が認められます。
保険会社は無職者の休業損害をゼロとすることが多いですが、裁判上は、就労の蓋然性を主張立証したら休業損害が認められることがあるので、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
⑥ 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
交通事故の被害者は、傷害を負い、一定期間治療を受けることを余儀なくされたことに伴う精神的苦痛に対して、損害賠償請求をすることができます。
・自賠責保険の基準
治療に要した日数に、1日あたり4300円をかけて算出された額が、傷害慰謝料として認められます。
・任意保険の基準
入院1日につき8600円、通院1日につき4300円とされることが多いです。
入通院の日数は、事故日から3か月以内であれば入通院の実日数とされ、事故日から3か月超6か月までの期間であれば入通院の実日数の75%とされ、事故日から6か月超9か月までの期間であれば入通院の実日数の45%とされ、事故日から9か月超13か月までの期間であれば入通院の実日数の25%とされ、事故日から13か月超の期間であれば入通院の実日数の15%とされることが多いです。
・裁判の基準
入院日数と通院日数から慰謝料の額を算定する表があり、その表に実際の入院日数と通院日数を当てはめて慰謝料額を算定します。
任意保険の基準に比べると、かなり高額になるので、保険会社から提示される額に安易に応じず、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
逸失利益
死亡事故の被害者は、死亡していなければ得られていたはずの収入が損害として認められ、被害者の相続人は、賠償請求することができます。
計算式
基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
基礎収入額
・給与所得者
原則として事故前の収入を基礎として算出されます。
現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、その平均賃金が基礎収入算出に用いられます。
若年労働者(概ね30歳未満)の場合には、まだ収入額が低いですが、死亡しなければ今後収入額が上がったはずとの考えから、原則として、全年齢平均の賃金センサスが用いられます。
・事業所得者
原則として申告所得額を基礎として算出されます。ただし、実収入額が申告額よりも高い場合には、立証があれば実収入額が基礎収入算出に用いられます。
また、現実収入が平均賃金以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスが用いられます。
・会社役員の場合
役員報酬は、労務提供の対価の部分と、利益分配の部分があります。そのうち、前者の労務提供の対価の部分は、給与所得者の給与と性質が同じなので、基礎収入額算出の基礎とされます。
一方、後者の利益分配の部分は、基礎収入額算出の基礎とされないことが多いです。
・家事従業者
女性労働者の全年齢平均の賃金額が、基礎収入算出に用いられるのが通常です。
兼業主婦の場合、実収入が女性労働者の全年齢平均の賃金額以上の時は、実収入により、実収入が平均賃金より低い場合は、平均賃金により算定します。なお、家事労働分の加算は認めないのが一般的です。
・学生、幼児等
男女別の全年齢平均の賃金額が、基礎収入算出に用いられるのが通常です。
もっとも、大学生になっていない人でも、進学校である高校に通っている場合や、両親が大卒者である場合など、被害者本人も大学に進学するのが通常であったと考えられる場合には、大卒者の平均賃金額が、基礎収入算出に用いられることがあります。
なお、女子年少者の逸失利益については、女性労働者の全年齢平均ではなく、男女を合わせた全労働者の全年齢平均賃金で、基礎収入が算定されるのが通常です。
・高齢者、年金受給者等
就労の蓋然性があれば、男女別、年齢別の平均賃金額が、基礎収入算出に用いられるのが通常です。
年金受給者は、年金額が基礎収入算出に用いられます。
また、受給開始前であっても、既に受給資格を有しているような場合は、年金額を基礎収入算出の基礎とすることができます。
・失業者
労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合は、再就職によって得られるであろう収入を基礎とすべきとされています。その場合特段の事情のない限り失業前の収入を参考にします。
ただし、失業以前の収入が平均賃金以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の平均賃金が基礎とされます。
生活費控除率
生活費控除率とは、被害者の方がもし生きていたのであれば、生活費として消費した費用のことをいいます。
死亡事故の場合には、生活費はかからなくなったわけですから、その分は、控除することになります。生活費控除率は概ね以下のように考えられています。
ただし、具体的な事情により、控除率は多少異なってくるので、注意が必要です。
① 一家の支柱
被扶養者1人の場合………………30%~40%
被扶養者2人以上の場合………………30%
② 女子(主婦・独身・幼児を含む)………………30%~40%
③ 男子(独身・幼児を含む)………………50%
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
就労可能年数は、人が労働によって収入を得るのが67歳までと考え、67歳から死亡時の年齢を引いて計算します。
死亡時の年齢が67歳を超える者については、原則として簡易生命表記載の平均余命の2分の1を就労可能年数とします。
ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずの金銭を前倒しで受け取るために得られた利益(中間利息)を控除するために使う指数です。
すなわち、逸失利益は本来であれば、毎年毎年発生していくものですが、民事裁判のルールでは、将来に発生する分も含めて一度に逸失利益の請求をしなければならないところ、将来受け取るはずの逸失利益を現在受け取ると、現在から将来までの期間に発生する利息(中間利息)を余計に受け取ってしまうことになります。
たとえば、10年にわたり毎年100万円ずつ逸失利益が発生する場合、最初に1000万円を一度に受け取ると、10年後には1000万円プラスその利息となり、100万円を10年にわたり毎年受け取るよりも多くを受け取ってしまうことになります。
そこで、基礎収入額に労働能力喪失率をかけたものに、労働能力喪失期間をやや短くした数字(ライプニッツ係数)をかけることとされています。
ライプニッツ係数については、以下の表をご覧ください。
なお、就労の始期については、18歳(大学卒業を前提とする場合は大学卒業予定時)とされますので、18歳未満の未就労者の逸失利益を計算する際は、以下の通りとなります。
計算式:男女別あるいは全労働者の平均賃金×(1-生活費控除率)×(67歳までのライプニッツ係数-18歳までのライプニッツ係数)
死亡慰謝料
基準額
死亡慰謝料については、一定の基準が定められています。
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他(独身の男女、子供、幼児等) 2000万円~2500万円
ただし、この基準は、あくまで一応の目安で、具体的な事情により増減されます。
また、この基準は、死亡慰謝料の総額であり、被害者を亡くしたことによる近親者の固有の慰謝料額も含まれています。
例えば、被害者本人に妻一人、子一人がいたという場合、被害者本人分の慰謝料が2600万円、妻固有の慰謝料が100万円、子固有の慰謝料が100万円の合計2800万円が認められるというようになります。
慰謝料増額の事由
加害者の運転態様が悪質な場合
例 無免許運転、飲酒運転、居眠り運転、著しいスピード違反、信号無視
加害者の事故後の対応が不誠実な場合
例 ひき逃げ、被害者を救護しないこと、証拠隠滅(加害車両の隠匿、廃棄、同乗者の口止めなど)、謝罪しないこと、虚偽の弁解など
被害者側に増額を認めるべき事情がある場合
例 被害者の遺族が精神疾患に罹患した場合、妻と小さい子を残して死亡した場合など
葬儀関係費用
被害者の遺族は、被害者の葬儀関係費用を支出した場合、その費用を請求することができます。
裁判実務では、原則として、葬儀関係費用は150万円とされ、150万円を超えて支出しても、原則として150万円とされます。
一方、実際に支出した額が、150万円を下回る場合、実際に支出した額が、葬儀関係費用として認められています。
なお、香典については、損益相殺(損害を被った者が、同じ原因で利益を得た場合、損害額から利益分が控除されること)を行わず、逆に、香典返しは、損害と認められていません。
弁護士費用
裁判になった場合、弁護士費用については、弁護士に支払った着手金と報酬金の合計額ではなく、「事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内」の額が損害として認められます。
裁判実務上は、判決で認められた全損害額の1割程度が弁護士費用にかかった損害額として認められます。
遅延損害金
裁判をした場合、遅延損害金(年5%)を、法律上、加害者に負担させることができます。